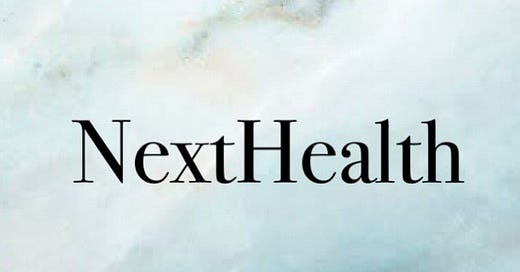今回は最近気になるニュースを3つ深堀してお届けします!
🔍注目ニュース1: Food as medicineの新時代
“Food as medicine”という用語はこの業界を追っている方なら馴染みあると思います。これまでは健康的な食事あるいは特定の疾患向けの栄養療法としたミールキットをシンプルに配送するサービスが主体でしたが、多様なプレイヤーがヘルスケアに参入していく中で面白い取り組みも増えてきたので、いくつか例をご紹介します。
① Instacart
食料品配送サービスとして有名なInstacartが、ただの宅配スーパーからパワーアップして、ヘルスケア事業に参入しています。特に力を入れているのが、健康に良い食材・レシピ、そして必要に応じて食事療法が必要な人に適した食料品を提供すること。サービス上に”Health&Wellness”といった健康的な食品のセクションを作ったり、栄養士とレシピを開発して掲載するだけでなく、なんと医療機関との連携まで開始しています。食事療法が必要な慢性疾患の患者さん向けに、医師がInstacard上で特定の食材に限って使える食料品クーポンを”処方”し、患者さんが指定された選択肢の中から食材を選ぶという仕組みです。直近ではハーバード大学附属のBoston Children’s Hospitalとの連携も発表しました。公的保険のMedicare & Medicaid、また、アメリカでは医療サービスの普及に大きな役割を担うVeterans Health Administration(退役軍人保健局)も導入に前向きだとニュースになっており、益々広い人口に届くサービスへと成長していく可能性が高いです。
③ Uber
配車サービスとして有名なUberも徐々にヘルスケアに参入していることが話題ですが、医療機関への移動手段の提供や処方薬の迅速な配送に限らず、Uber eatsを活用したfood as medicineへの進出も見逃せません。具体的には今後健康的な食事や食材の配送のプログラムを作っていくとのことで、こちらも公的保険Medicare & Medicaidから注目されています。まだ具体的な事業の発表はされていないので、今後もチェックしていきたいところです。
③ L-nutra
こちらはもともとダイエット・長寿食を提供していたD2Cの会社。ファスティングが長寿に貢献するということが注目されている中、実際に断食するのではなく、ファスティング様のメタボリズムを作り出すようなダイエット食を開発しています。そこから派生して、ファスティングが糖尿病・アルツハイマー・がんなどの慢性疾患にも貢献することを研究しており、この栄養食と一般的な食事療法、オンライン診療などを組み合わせたfood as medicineサービスに乗り出しています。こちらもすでに保険償還が進んでおり、保険者としても食事療法で慢性疾患患者の医療費削減をしていくことには前向きだということが良くわかります。
🔍注目ニュース2: 腎臓病関連のイノベーションに注目
慢性腎臓病の患者さんはその他生活習慣病を含め合併症を多く抱えており、健康維持のためにも医療費削減のためにも、総合診療的な視点で診療し、イノベーションを推進してくことが重要な領域です。そのような背景を受けて新たな動きをふたつご紹介。
1つめは、Value Based Careの有名企業Oak Street Healthが、腎臓ケアの企業Interwell HealthとJVのOakWellを立ち上げたニュース。重症慢性腎臓病患者に対するプライマリーケアの事業を開始しました。透析を受けている患者さんはそれだけでもかなりの通院の負担があり、これに加えて他院・他科を受診するのは一苦労。一方管理・コンプライアンスが不十分だと入院や腎移植など、医療費も高額となるリスクを抱えています。このような課題に切り込むため、OakWellは透析センターにいる時間を活用してプライマリーケアを提供し、総合的な視点で患者さんを管理していく予定です。
2つめも、JVです。透析センターの運営など腎臓ケアの企業DaVitaと医療機器メーカーMedtronicが、腎臓テックに取り組むJVのMozarc Medicalを立ち上げました。両社がそれぞれ$200M出資しており、名前は音楽界に永久のインパクトを残したモーツァルトが由来とのことです。DaVitaが持つ慢性腎臓病患者へのアクセスとMedtronicの医療機器の知見を掛け合わせて、患者さんがより暮らしやすくなるための在宅透析テックや、腎臓病の原因となる生活習慣病や社会的格差などの根本解消を目指すテクノロジーを開発したいとのことですが、詳細についてはまだ未公開のため今後に期待です。
🔍注目ニュース3: DTxのパイオニアPear Therapeuticsが倒産
2014年に立ち上がった同社は、薬物依存症や不眠症などに対するFDA承認されたアプリを開発しており、2021年にSPAC上場。アプリが薬剤のように処方され保険償還される世界を目指していたものの、倒産に。90%の社員はレイオフされて現在買主を検討中。臨床医側は処方したいと思ってくれていたものの、保険償還が思い通り進まず=売上が確保できず。同社のアプリを使うことで入院などを抑制し短期的なコスト削減を示すことは出来たのですが、長期的な保険会社に対してのメリットの説得力が足りず。4.5万件処方がされた中、約半分しか実際活用されず、そのうち41%しか保険償還されなかったとのこと。特に、公的保険のmedicareがDTxを償還してくれないのが大きかったとのこと。ここ1-2年でデジタルヘルスのバブルが崩壊したという背景もあり、グロースステージ全体的に厳しい環境だったとは思います。これからのDTxは益々長期的な臨床的意義と経済的メリットのエビデンスを構築して保険者を説得していくことが重要になってきそうです。いくらデジタルヘルスが流行ってるとはいえ、流されずに、臨床的価値・既存治療法に対する優位性がなによりも大事と思い知らされる一件だったと思います。[参照記事 1 2 3]
それではまた次回もどうぞよろしくお願いいたします。